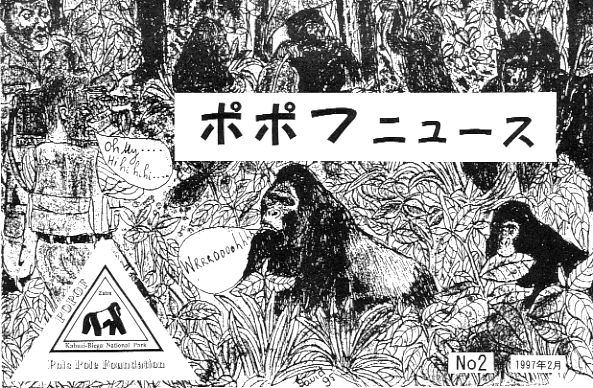|
|
|
| ポポフ(POPOF)はポレポレ基金(Polepole Foundation)の略称1992年にザイール共和国で設立されたNG0(非政府・非営利団体)一。ポレポレとは「ぼちぼち」という意味のスワヒリ語で、あせらずにゆっくりと連動の輪を広げていこうという気持ちがこめられます。
ポフポフの目的は、ザイール東部にあるカフジ・ビエガ国立公園の.で自然現境の保全、絶滅の危機に瀕する東ローランドゴリラの、地域振興、自然保護教育を実践することにあります。会員はほとんど国立公園周辺に居住する地元の人々で、調査団をして土壌や動植物相の現状を調査したり、観光客に配布するパレットや絵はがきをつくったり、地元でエコ・ツーリズムを推進するための活動をしています。 こういったポポフの活動を支援するために、日本支部ではカフジ・ビエガ国立公園や東ローランドを紹介するパンフレットや絵はがを作成して販売し、展示会、講演会を開いて寄付金を募り、現必要な物品を購入する資金にあてています。また、民芸品を作る技術やアイデア、自然保護教育のための教材を提供したりします。日本ではまだポポフの会員を募集するまでには至っていんが、将来日本からも人材を派遣してより国際的な活動ができうにしていきたいと思っています。 ポポフニュースは、最近のポポフの活動を紹介し、今までに日本められた責金がどのような活動に使われたかを報告するニューレターです。現地の人々やゴリラの近況についても報告していと思います。また、ポポフが創作したポポフグッズや絵はがき販売についても紹介いたしますので、お知り合いで輿味のある方ぜひ伝えていただきたいと願っています。
|
活動報告
上野動物園(東京)
講演:「野生ゴリラの生態と保護」
山極寿一(京都大学霊長類研究所)
1996年6月一7月
「アフリカ・フェア」ヘポポフ・グッズ出展 ウィルあいち、風'S(名古屋)
1996年7月23日一28日
「ザイールのアートとポポフ」展 堺町画廊(京都) 7月28日 講演:「ゴリラの森に暮らす」 山極寿一(京都大学霊長類研究所)
「ザイールの伝統社会と自然保護」
バサボセ・カニュニ(ザイール中央科学研究所)
1996年8月12日一18日
堺町画廊(京都) 国際霊長類学会 ウィスコンシン大(米国) 発表:「東ローランドゴリラの保護の展望」 山極寿一(京都大学霊長類研究所)
「東ローランドゴリラの保護政策と案状」
マンコト・マ・オイセンズウ(ザイール自然保護局)
1996年9月20日
次世代の動物園を考える会 フロイデ(犬山) 講演:「ゴリラの保護と人々の暮らし」 山極寿一(京都大学霊長類研究所)
1997年2月11日一3月15日
「ゴリラのすむ村」展 上野動物園 (株)カヨー・コーポレーションが、販売するゴリラのぬいぐるみが一っ売れる毎に1米ドルをポポフに寄付してくれることになっています。ポポフとしてはこの販売にポポフのマークを使用することを了承しています。 名古屋の風'sや京都のクレエなど、ポポフの主旨に賛同していただいたいくつかのお店にポポフ・グッズを置かしていただき、委託販売をしています。 |
|
1
|
|